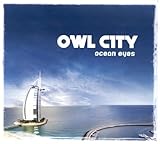Goldmund / Malady of Elegance (2008年)
今回紹介する名盤は「Helios」「Mint Julep」「SONO」などの名義で活動するKeith Kenniffのソロプロジェクトからのアルバムです。
ジャンル
ポストクラシカル
ポストクラシカル
アンビエント
エレクトロニカ
アメリカ
Keith Kenniff

アーティスト
Heliosでの活動が最も有名かと思われますが、Goldmundも皆様に知って欲しいと思うのです。
Keith Kenniffはギター、ベース、ドラム、ピアノなど少年時代からさまざまな楽器を演奏し、青年期に入りバンド活動を始めます。
その中でロックやジャズ、クラシックなど幅広い音楽に触れ、自分の求めていた音楽を知ります。
端的に言うと「Helios」はアンビエント+エレクトロニカ「Goldmund」はポストクラシカル「SONO」はポストロック「Mint Julep」はシューゲイザーといった感じで名義によって異なる音色を奏でています。
また、本人名義でアップルやフェイスブック、グーグルのCM音楽や映画音楽など作曲し、日本でも様々なテレビ番組でKeith Kenniffの音楽はBGMとして使われています。
Keith Kenniff名義ではHeliosとGoldmund
が合わさったような音世界です。
アルバム
Heliosのセンチメンタルなメロディーセンスなどはそのままに、楽器をシンセなどの電子機器などではなく、レトロなピアノの音のみで作り出します。
アーティスト
Heliosでの活動が最も有名かと思われますが、Goldmundも皆様に知って欲しいと思うのです。
Keith Kenniffはギター、ベース、ドラム、ピアノなど少年時代からさまざまな楽器を演奏し、青年期に入りバンド活動を始めます。
その中でロックやジャズ、クラシックなど幅広い音楽に触れ、自分の求めていた音楽を知ります。
端的に言うと「Helios」はアンビエント+エレクトロニカ「Goldmund」はポストクラシカル「SONO」はポストロック「Mint Julep」はシューゲイザーといった感じで名義によって異なる音色を奏でています。
また、本人名義でアップルやフェイスブック、グーグルのCM音楽や映画音楽など作曲し、日本でも様々なテレビ番組でKeith Kenniffの音楽はBGMとして使われています。
Keith Kenniff名義ではHeliosとGoldmund
が合わさったような音世界です。
アルバム
Heliosのセンチメンタルなメロディーセンスなどはそのままに、楽器をシンセなどの電子機器などではなく、レトロなピアノの音のみで作り出します。
要はHeliosのアナログバージョンとでも言いましょうか。
音楽聴きたいけど、どれもうるさく感じる。
でもアンビエントでは物足りない時に私はよく聴きます。
寝る時にかけると深い眠りに誘ってくれます。
深い海の底に沈んでいるレトロなピアノを奏でたかのような音です。
音が空気に包まれながらポコ…ポコ…と水面を目指しゆっくり上がっていくイメージです。
In A NotebookPR
Sting / Nothing Like the Sun (1987年)
今回紹介する名盤は2003年にロックの殿堂入りを果たした元The Policeのベーシスト兼ヴォーカルとして活躍したアーティストのアルバムです。
ジャンル
ジャズロック
ロック
ニューウェーブ
アーティスト
Stingがグラミー賞を取るので、嫉妬したRod Stewart「彼らは、スティング以外の英国人には賞を与えないつもりなんだ。 インディアンに親切なミスター・シリアス以外にはね」 と自分がグラミー賞を貰った事が無いのでこんなことを言いました。 この発言に対しStingは「彼はグラミー賞を受賞するに値する。ほんとにそう思うね。 彼には僕のを1つ送ってやろうかと思ってる」と皮肉の効いたユーモア溢れる返しました。
Stingとは本名ではなく通称で本名はGordon Matthew Thomas Sumnerというそうです。
なぜStingと呼ばれるようになったかというと黄色と黒色のボーダーの服を好んで着て、それが蜂みたいということで「チクリと刺す」という意味でStingと呼ばれるようになったそうです。
2002年に開催された冬季オリンピックのオープニングで世界的チェリストであるYo-Yo Maと「Fragile」を共演しました。
9.11の同時多発テロの直後だったのもあり、大勢の人々に感動を与えました。
因みにジョジョの奇妙な冒険 第三部に出てくる花京院典明の好きなミュージシャンはStingです。
因みにジョジョの奇妙な冒険 第三部に出てくる花京院典明の好きなミュージシャンはStingです。
アルバム
本作はStingが関わったアルバムの中でも1、2位を争うくらいの完成度です。
まず、このアルバムの参加者がすごいんです。
マイルスの知恵袋と呼ばれた編曲者
「Gil Evans」
ジャズやロックの数々の著名人と共演をしてきた
「Kenneth Kirkland」
言わずと知れたギターの神様
天才ジャズサクソフォーン奏者
「Branford Marsalis」
などここではあげきれないくらいの著名人が参加しています。
あの批評家Miles Davisが「出来がいいのはGil Evansがアルバム製作に参加しているからだ」認めるくらいの完成度です。
本作の3曲目「Englishman In New York」は多くの人達がカバーするほどの名曲です。
聴けば聴くほど味がするプロ集団が巧みに作り上げた若者には出せない味のある大人なロック名盤を是非。
#3 Englishman In New York
#6 Fragile
関連記事
Sting / Ten Summoner's Tales (1993年)
#3 Englishman In New York
#6 Fragile
関連記事
Sting / Ten Summoner's Tales (1993年)
DJ Shadow / Endtroducing.... (1996年)
今回紹介する名盤は英国音楽誌NMEで「ギターをサンプラーに持ち替えたジミ・ヘンドリックス」との異名を持つDJのアルバムです。
ジャンル
ヒップホップ
ヒップホップ
アーティスト
また彼のことを「King Of Diggin'」(レコード掘り)と呼ぶ人もいます。
彼の凄いところは少なくとも4つあります。
⚪既存曲の豊富な知識
⚪音選びのセンス
⚪数多ある音を選びサンプリングして1曲にする技術
⚪またそれを1つの世界観でアルバムにする能力
昔私はヒップホップのことを「他人のふんどしで相撲取るなんて」と馬鹿にしていましたが、それは大きな間違いでした。
既存の曲を使い自分のオリジナルを作曲しなければならないという縛りは一筋縄ではいかないのです。
例えるならば、もう出来上がってる料理から少しずつ取って混ぜて絶品料理を作るようなものです。
アルバム
本作は普段ジャズやロックを聴いていてヒップホップというだけで敬遠してる人にこそ聴いて欲しいアルバムです。ラップが気に入らなくてヒップホップを聴かない人も大丈夫、基本インストなので耳障りなラップなどはありません。
本来ならこのまま消えてなくなる音を掬い上げられて、別の形で世の中に使われていくヒップホップというのはとてもエコな音楽なのではないでしょうか。
埃まみれの50万枚以上のレコードから吟味して掘り出された音を何層にも重ねて編集されて作られた名盤を是非。
#9 Organ Donor埃まみれの50万枚以上のレコードから吟味して掘り出された音を何層にも重ねて編集されて作られた名盤を是非。
Brian Eno / Ambient 1: Music for Airports (1978年)
今回紹介する名盤はアンビエントという音楽ジャンルを確立させたアルバムです。
ジャンル
アンビエント
ミニマルミュージック
ニューエイジ
現代音楽
アーティスト
日本人にとってBrian Enoほど知名度と楽曲が聴かれている差の大きいアーティストもいないでしょう。
というのも、マイクロソフトの「Windows 95」の起動音は彼が作曲しました。
この時のマイクロソフトから出された条件は「人を鼓舞し、世界中の人に愛され、明るく斬新で、感情を揺さぶられ、情熱をかきたてられるような曲を御願い致します。ただし、長さは3秒コンマ25ね。」でした。
もういくらなんでも無理難題です。
これにはBrian Enoもだいぶ頭を悩まして、最終的に84個のとても短いフレーズが作曲され、その中の一つが使われています。
またDavid BowieやTalking Heads、U2などをプロデュースして高評価を受けました。
今でこそアンビエントの先駆者や敏腕プロデューサーというイメージですが、デビュー当時は奇抜なファッションでグラムロックをしていました。
このアルバムの聴き方は「聴こうとせずに聴き流す」です。
そもそもアンビエントというジャンルは鑑賞用ではなくインテリアになりうる音楽だそうです。
なんで「聴かない音楽」という矛盾とも取れる音楽が生まれたかと言いますと、Brian Enoが交通事故に遭い入院生活の中でレコードの音量のコントロールや停止させたり出来なかったという体験から「聴くことも出来るし、聴かないこともまた容易い音楽」という新しい音楽の関わり方が生まれたのです。
アルバム
このアルバムを直訳すると「空港のための音楽」です。
これはアルバムのイメージとかではなく、Brian Enoが空港のBGMとして作曲したものです。
実際にニューヨークにあるラガーディア空港で使用されているそうです。
私は音楽を好んでずっと聴いていると極稀に何も聴きたくない時があります。
そんな時本作を流しながら気持ちをリセットします。
静かに過ごしたい時、外の喧騒が気になる時このアルバムをかけてみて下さい。
きっとさっきより静かに感じるはずです。
Owl City / Ocean Eyes (2009年)
ジャンル
シンセポップ
エレクトロニカ
アメリカ
Adam Young
今回紹介する名盤はエレクトロニカ界のメッシことAdam Youngのソロプロジェクトのデビューアルバムです。
アーティスト
Adam Youngは映画「ガフールの伝説」のテーマ曲を作曲したり、ディズニー映画の「シュガー・ラッシュ」の作曲の指名を受けたり、ピアノエモというジャンルで絶大な支持を受けているバンド「Mae」の前座をつとめたりと、まだ若いのに圧倒的信頼を得ています。
日本でもアサヒドライゼロのCMでCarly Rae Jepsenとのコラボ曲「Good Time」が使われています。
そして、日本テレビの「スッキリ」でも紹介され日本でも知名度を徐々に上げてきている。
また2012年にはフジロックフェスティバルに、2014年にはASIAN KUNG-FU GENERATIONが主催しているロックフェスNANO-MUGENに出演したりとAdam Youngは来日をたくさんしています。
よく比較される「The Postal Service」は玄人向けだと思いますが、Owl Cityは洋楽初心者でも気に入ること間違い無しのキャッチーなメロディーが満載です。
もし電子音が苦手という人は別名義のプロジェクト「Sky Sailing」を聴いてみて下さい。
こちらは生楽器で演奏することをコンセプトに作られたプロジェクトです。
こちらも爽やかなサウンドで聴いていてとても気持ちいいです。
なんとSEKAI NO OWARIとのコラボ曲「Tokyo」が2014年の11月5日に配信されるとのことです。
ここから洋楽ファンが増えることを願います。
アルバム
このアルバムはアメリカだけで100万枚以上を売上プラチナディスクに認定されています。
私の中でエレクトロニカは冬の音楽というイメージなのですが、このアルバムは珍しいことに夏にピッタリのアルバムになっております。
ジャケットも海のデザインですし夏に昼間にドライブして風を感じながら聴くのが最高だと思います。
本作の9曲目「Fireflies」はアメリカを含む世界23カ国でチャート1位を獲得し、全世界で1,200万枚の売上を記録しました。
「Fireflies」も勿論いいのですが、私は疾走感を感じる「Cave In」爽やかなサウンドで海を感じる「On The Wing」ピコピコキラキラの「Hello Seattle」が好きですね。
爽やかに流れる風のようなサウンドにAdam Youngの癒し系ボイスを乗せて作られる音世界。
夏に聴けるエレクトロニカという希少な名盤を是非。
23ヵ国で1位を獲得した曲
海を感じる曲
23ヵ国で1位を獲得した曲
海を感じる曲
プロフィール
HN:
おけす
性別:
非公開
カテゴリー
最新記事
(07/06)
(06/07)
(05/30)
(05/29)
(01/11)