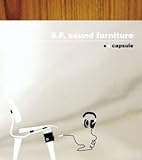CAPSULE / S.F. sound furniture (2004年)
今回紹介する名盤はPerfumeやきゃりーぱみゅぱみゅなどのアーティストをプロデュースしているアーティストのアルバムです。
ジャンル
ハウス
エレクトロニカ
テクノポップ
日本
中田ヤスタカ
CAPSULEは作曲や演奏、ジャケットデザインその他諸々を中田ヤスタカが担い、ボーカルをこしじまとしこが担当するテクノポップユニットです。
中田ヤスタカを知らない人は多いかも知れませんが、今の日本で中田ヤスタカが作曲した音楽を聴いたことない人の方が少ないはずです。
ドラマや映画にもなった「LIAR GAME」のサントラだったり、「どうぶつ奇想天外!」の音楽を手掛けたり、細かい所を言うと北陸新幹線金沢駅の発車する時に鳴るメロディーもそうですし、上記したように「きゃりーぱみゅぱみゅ」や「Perfume」の曲のほとんどは中田ヤスタカ作曲であります。
そんな中田ヤスタカがメンバーとして活躍しているプロジェクトがCAPSULEなのです。
私がCAPSULEを知ったのは「吉幾三」「CAPSULE」「Daft Punk」「Beastie Boys」の曲をマッシュアップした動画でした。
漫画「ONE PIECE」の作者 尾田栄一郎と親交があり、雑誌で対談をしたり「ONEPIECE展」や映画「ONE PIECE FILM Z」で曲を提供したりしています。
因みにジョジョの奇妙な冒険 第七部 スティール・ボール・ランに出てくるディ・ス・コのスタンドは中田ヤスタカが作曲したPerfumeのチョコレイト・ディスコが元ネタです。
アルバム
本作はCAPSULEの4枚目のアルバムでコンセプトは「仮想未来の家具のような音楽」ということで音楽をかけていて邪魔にならないジャズテイストの7曲目「壁に付いているスイッチ」やボサノヴァテイストの10曲目の「Ocean Blue Sky Orange」曲が多いです。
Starry Skyのような尖ったCAPSULEではなく、柔らかい感じの曲が多いです。
スタジオジブリによるハウス食品のCM「おうちで食べよう」シリーズで使用された最後の「レトロメモリー」が私は1番好みでした。
未来旅行に連れてってくれるピコピコの名盤を是非。
レトロメモリー
PR
Justin King / Le Bleu (2001年)
今回紹介する名盤はMichael Hedgesのスタイルの全てをマスターし、それを更に発展させつつある超絶テクニシャンと評されるギタリストのアルバムです。
ジャンル
アコースティック
ニューエイジ
ワールドミュージック
アメリカ
Justin Kingは10代のころからドラムやギターを始め、アコースティックギターを本格的に始めたのは19歳頃でありました。
そして、現在も付き合いのあるDrew Dresmanと作曲や演奏など音楽活動を行っていました。
20歳になると早くもデビューアルバム「Justin King」を発表し、翌年には「Opening」を発表します。
その後Justin Kingはヨーロッパ各地を旅して周り、世界のいろいろな音楽に触れます。
そして、自分の音楽世界を大きく広げた後にフラメンコやケルト音楽を取り入れたインストゥルメンタルアルバム「Le Bleu」を発表します。
「Le Bleu」を収録したスタジオを気に入ったJustin Kingはアメリカに帰ると約2年をかけて自分のスタジオを作りました。
その間はJames TaylorやB. B. King、Diana Krall、Al Greenなどの前座を務めたり、アメリカをツアーで周ったりしていました。
スタジオが完成するとCarlos VamosとMichael Manringとともに「I-XII」をレコーディングします。
この頃からソロ活動の他にバンドを組んだり、他のアーティストとコラボしたり、ギター以外のキーボード、ベース、ドラムなどの楽器を一人で演奏をしたりと様々な挑戦をしていきます。
その探求心はとどまることを知らず、2007年からフォトジャーナリストとして活動を始め、2008年にはイラクの戦場で臨場感ある写真を撮り続けウェブサイトやニュース雑誌などで使用されました。
そして、現在は大学で油絵と写真の勉強をされているそうです。
アルバム
本作はJustin Kingを一躍有名にしたアルバムであります。
Justin Kingがなにから人気に火が付いたかというとYouTubeにあげられた「Knock on Wood」「Phunkdified」「Loco Motives」の演奏技術の高さでしょう。
そして、演奏をしているJustin Kingのルックスの良さもあると思います。
上記した3曲もいいですが私は3曲目の「After the Harvest」と8曲目の「Amazing Grace」の透き通るようなアコギサウンドが好みです。
本作は基本インストゥルメンタルなのですが、最後の曲「Ashes」はJustin King本人が歌っているのですが、これがまた腹立つほどイケメンボイスでまだこんな武器を隠していたのかと驚きました。
アコギと歌声だけで表現するヨーロッパ周遊へと連れていってくれる名盤を是非。
Knock on Wood
Knock on Wood
Libera / Libera (1999年)
今回紹介する名盤は天使の歌声を持つ少年合唱団のアルバムです。
ジャンル
クラシカル クロスオーバー
ポップオペラ
聖歌隊
イギリス
Liberaという言葉はラテン語で「自由」という意味が込められ作曲家Robert Prizemanが指揮を執る40人ほどで編成される少年合唱団です。
このLiberaとしてのプロジェクト自体は3形態目で1984年にThe St. Philips Boy's Choirとして活動を開始して1990年にAngel Voicesへと変わり、1998年に現在のLiberaとなります。
Liberaのトレードマークと言えば天使のような真っ白なローブですが、これはAngel Voices時代からの名残になります。
少年合唱団というと真っ先に思い浮かぶのはウィーン少年合唱団だと思いますが、私はLiberaの方が好みでした。
というのもAngel Voices時代までは普通の聖歌隊だったのですがLiberaからはハウス的なビートを大胆に取り入れたサウンドが新しかったからです。
ウィーン少年合唱団は声変わりしたら終わりですが、Liberaは低音パートがあるのでそのまま活動を続けたりボイストレーナーやコンサートスタッフとしてなど何らかの形でLiberaに残れるのです。
その他にもウィーン少年合唱団の黒い噂で素直に音楽そのものを楽しめなくなってしまったというのもあります。
やはり音楽は楽しくないとね。
因みに海外で支持が高い「ICO」というゲームの主題歌を歌っているSteven GeraghtyはLiberaのメンバーです。
アルバム
本作はLiberaと改名して1発目のアルバムで私は本作が1番好きです。
何故なら、本作以降少しずつ打ち込みビートが無くなっていきます。
当然歌声だけで素晴らしいんですが、隠し味の電子音が非常にいい味を出しているんです。
Enigmaの「MCMXC a.D. 邦題 永遠の謎」のような雰囲気が好きならきっと気に入ることだと思います。
自由に音で遊ぶ天使達の歌声が聴ける名盤を是非。
Libera
Libera
Helios / Eingya (2006年)
ジャンル
ポストクラシカル
アンビエント
エレクトロニカ
アメリカ
Keith Kenniffはギター、ベース、ドラム、ピアノなど少年時代からさまざまな楽器を演奏していました。
そして、青年期に入るとバンド活動を始めます。
その中でロックやジャズ、クラシックなど幅広い音楽に触れ、自分の求めていた音楽を知ります。
Keith Kenniffはアメリカ ボストンの名門バークリー音楽院で打楽器を専攻しました。
日本のいろいろなテレビ番組やCMでもKeith Kenniffの音楽はBGMとして使われています。
HeliosはKeith Kenniffが使っている名義の中では1番知名度があるのではないかと思います。
Goldmundはセンチメンタルなメロディーをレトロなピアノで奏でていきますが、Heliosはギターを主体としています。
ポストクラシカルに近いエレクトロニカといった感じでアンビエントよりメロディーがあるけれど、エレクトロニカより優しく落ち着いているといった調度良い具合の曲ばかりです。
Keith Kenniffはどの名義でもアルバムジャケットが素敵で思わず飾りたくなりますし、音ともリンクしているのでジャケ買いしても失敗はありません。
アルバム
本作はKeith Kenniffの代表名義Heliosの中でも1番人気の高いアルバムなのでKeith Kenniff入門には持ってこいの作品です。
上記したようにアルバムジャケットと音がリンクしているので、まずジャケットを見てみましょう。
男女が手を繋ぎ海を眺めている絵、私はこれを写真ではなく絵にしたことでより柔らかいイメージがして好きです。
私はこのアルバムを聴くと無性に喪失感に襲われます。
なので、私が本作に持つイメージは恋人がもう側にはいなくて、海を眺めながら過去の思い出に耽っている感情を音で表現したといった感じです。
大事な人がなくなったの時の言葉では表すことが出来ない複雑な感情図をギターとピアノ、少しの電子音、そして鳥のさえずりに川のせせらぎで紡ぎ出し表現した名盤を是非。
Goldmund / Sometimes (2015年)
Goldmund / Malady of Elegance (2008年)
The Toy Garden
Goldmund / Sometimes (2015年)
Goldmund / Malady of Elegance (2008年)
The Toy Garden
Hiromi Uehara / Another Mind (2003年)
今回紹介する名盤は「ロック、ファンク、ジャズ、パンクと音の力を究めた」と言われる演奏をする日本人女性ピアニストのアルバムです。
ジャンル
ジャズ
プログレッシブジャズ
日本
上原ひろみは6歳からピアノを始め、小学校の高学年の時には学校の音楽会で「おどるポンポコリン」を発表するため、編曲や楽器パートの譜面作りなど自分一人で全てやってしまうほどでした。
この頃は鍵盤の皇帝Oscar Petersonやビハインド・ザ・ビートと呼ばれるErroll Garnerなどのジャズを好んで聴いていました。
しかし、高校時代はFrank ZappaやDream Theater、King Crimson、Jeff Beck、Sly & The Family Stoneロックも好んで聴くようになり音楽の幅が広がります。
そして、16歳の時に上原ひろみにとって運命的な出会いと言えることが起こります。
すると上原ひろみの演奏に感銘を受けたChick Coreaも演奏を始めて、その場で即興での共演となりました。
そして、Chick Coreaの来日公演の最終日に上原ひろみをステージ上に呼んで観客の前で共演を果たします。
上原ひろみの演奏技術も凄いですが、私はその場で演奏出来る心の強さ、度胸に関心します。
余程自信がないと萎縮して演奏しないか、もし演奏をしても普段の力を発揮できないはずです。
そして、心の強さも然る事ながら器の大きさも凄くて、コンサートの演奏中に観客の携帯が鳴り響いてしまったのですが、上原ひろみはその着信音を演奏の中に織り混ぜて演奏を続け、観客に笑顔で応えました。
上原ひろみの快進撃はデビュー作「Another Mind」は日本ゴールドディスク大賞でジャズアルバム・オブ・ザ・イヤーを受賞したのを始め、2004年発表「Brain」はアメリカで「サラウンド・ミュージック・アワード」を受賞し、その後もグラミー賞を含め数々の賞を受賞していきます。
アルバム
本作はそんな上原ひろみのデビュー作でコンセプトは「ピアノトリオの限界」です。
上原ひろみは童顔で見た目は可愛らしい子どもみたいですが、1曲目の「XYZ」を聴くと打ちのめされること間違いなしです。
想像を絶するアグレッシブな演奏で変拍子に次ぐ変拍子で、そこら辺のプログレバンド顔負けの曲になっています。
プログレバンドを一掃してしまうほどの超絶技巧を魅せてくれるピアノトリオの名盤を是非。
XYZ
XYZ
プロフィール
HN:
おけす
性別:
非公開
カテゴリー
最新記事
(07/06)
(06/07)
(05/30)
(05/29)
(01/11)